発達障害スクリーニング検査の結果を聞いてきました
先日、休職中に発達障害スクリーニング検査を受けてきました。
その経緯については以前の記事にまとめていますので、よければそちらもご覧ください。
そして今日は、その検査結果を聞きに病院へ行ってきました。
2時間待ちのあと、診察はわずか1分
朝から予約を入れて向かったものの、診察室に呼ばれるまで約2時間待ち。
ようやく順番が来たと思ったら、医師の口から出たのはとてもあっさりした一言でした。
「ASDの傾向は低いですね。診断名がつくほどではありません」
診察自体はわずか1分で終了。
思わず「なんだそりゃ」と感じましたが、「大きな問題はなかった」という意味ではホッとしました。
拍子抜けと安心感、その両方を感じた
これまで私は「もしかするとASD傾向があるのでは」と思い込んでいました。
妻からの指摘や、自分で感じていた特性の強さもあり、半ば納得していた部分もあったからです。
だからこそ結果を聞いたとき、拍子抜けと安心感が同時に押し寄せたのが正直なところです。
診断名より大切なのは「特性の理解」
診断名がつくかどうか以上に、私にとって大切なのは「自分の特性を理解し、どう扱うか」でした。
- 考えすぎてしまう
- 人に振り回されやすい
- 不安に意識を持っていかれやすい
こうした傾向は診断の有無に関係なく存在します。
だからこそ、これらを特性として受け止め、日常の中でコントロールしていくことが重要だと気づきました。
例えば…
- 感情が揺れて思考が暴走しそうになったら「今反応している」とラベリングして一呼吸置く。
- 摩擦を恐れて溜め込むのではなく、こうして文章にして外に出す。
こうした小さな実践こそが、生きやすさにつながるのだと思います。
息子とのキャッチボールで感じた安心
病院の帰りには、息子と公園でキャッチボールをしました。
友達も一緒にボールを投げ合い、笑い合う姿を見て、父として本当に嬉しくなりました。
その後のピッチング練習も復調していて、週末の大会に向けて期待が高まります。
こうした家族との時間が、私にとって「これでいいんだ」と思える大きな支えになっています。
仕事復帰を前にして感じたこと
夕方には同僚との打ち合わせもありました。
「頑張りましょう!」という言葉を繰り返し聞き、正直少し疲れる部分もありましたが、
私は私のやり方で「聴ける人柄」を活かして働けばいいと改めて確認できました。
復職を控えて不安もありますが、今の合言葉は 「動けば整う」。
無理をせず、マイペースで淡々と進めていこうと思います。
まとめ
今回の発達障害スクリーニング検査の結果は「診断名はつかない」というものでした。
しかし私にとって大切なのは、診断に頼ることではなく、自分の特性を理解して整えていくことです。
これからも「反応に気づき、手放す」習慣を持ちながら、仕事も家庭も一歩ずつ前に進めていきます。
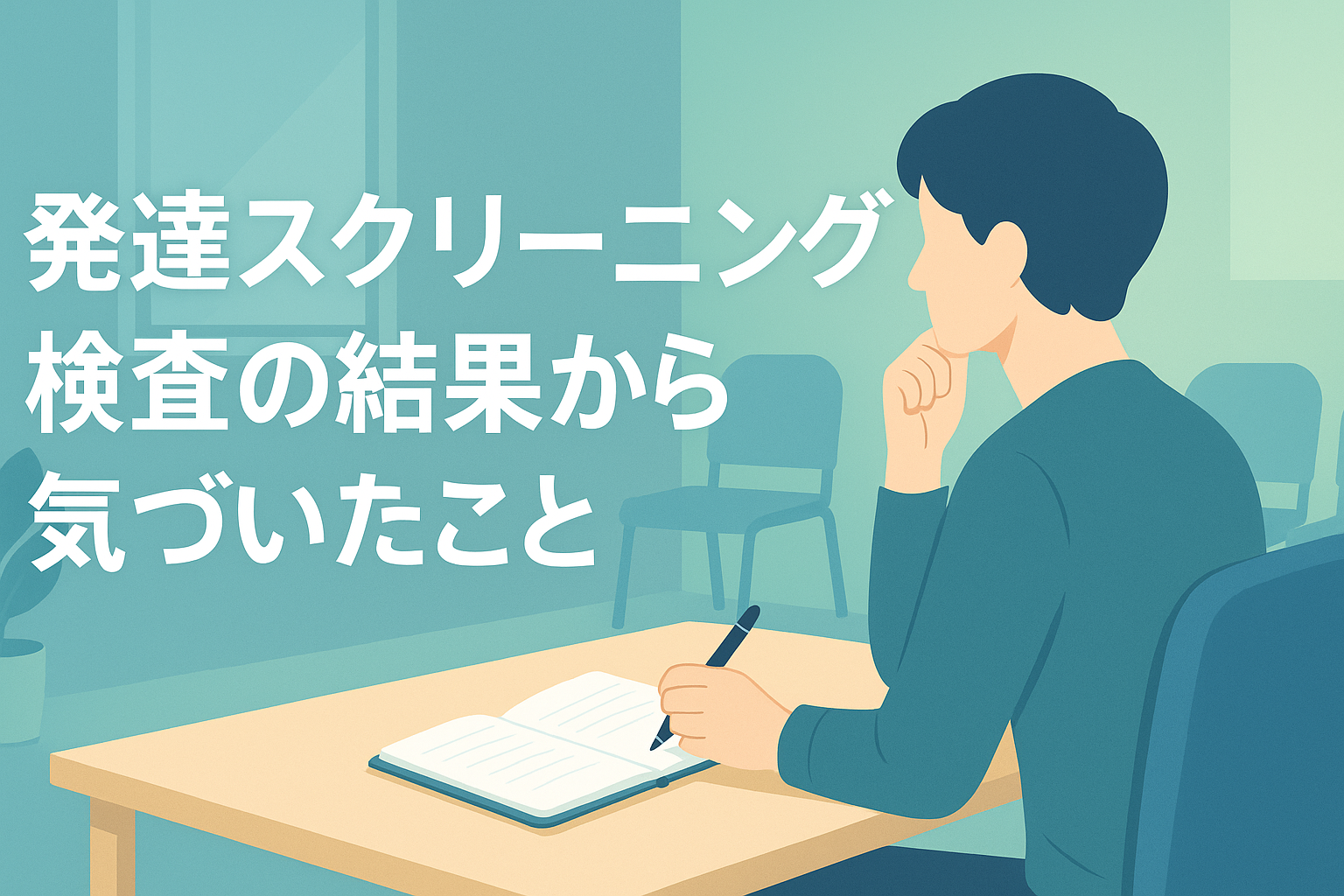


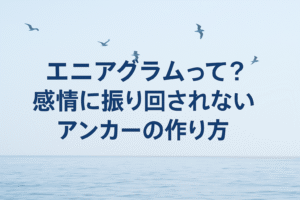

コメント