仕事のストレスで休職し、適応障害と診断されました。
最初は「自分が弱いからだ」と思っていましたが、実は 自分の特性 が関係していたのです。
この記事では、その体験と気づきを正直に書いていきます。
転職と混乱のはじまり
僕は今、適応障害で休職しています。
最初は「自分が弱いからだ」「逃げてしまった」と思っていました。
でも振り返ってみると、それは弱さではなく、私の“特性”によるものだったと気づきました。
数か月前、僕は大規模な医療系の組織に転職し、事務長ポジションを担うことになりました
そこで待っていたのは、曖昧な指示を繰り返す上司でした。面接のときは、攻めか、守りか、どちらのタイプ?と聞かれてどちらかというと守りのタイプです。と正直に伝えていました。300名規模の法人の管理をするのは大変だろうなとは思いつつも、現場で売上を上げるよう牽引していくマネージャーの役割もあるとなると、並行しての業務は困難だとすぐに気が付いたので、どちらをやりますか?と上司に言われ、業務がある程度確立と思われる事務の業務で事務長職、その中でもキャリアコンサルタントの資格が少しは活かせる人事労務の部分でまずは現場を知ることから始めさせてもらいたいと伝えました。
事務局には各担当が少人数で配置されていました。経理のおばちゃんはそろそろ定年。親の介護もあったりと、退職リスクもありそうです。その他の人とは時間を少し作ってもらい、1on1で話を聴いていると、この事務局の人たちはM&Aで買収された側の人だったことがわかりました。そこに外部から理事長秘書、マネージャー、事務長すべての役割でその上司が入ってきた模様。もともとのスタッフが倍になり、業務の負担も増えていることがわかりました。
事務局の崩壊とストレス
しばらく現場に入って法人のルールを統一していくことから始めないと一本化はできないなと思い、組織図や就業規則などを確認しましたが、それも「ない」とのこと。心がざわついてきましたが、話を聴いていく中で、給与計算のことでなにやら労務担当がかなり追い込まれているようでした。
労務コンサルがオンラインでフォローに回っているにもかかわらず、なんでこんな状態?と思いつつも、言われるがままにひとまず僕は人事労務の責任者としてやってくださいとのこと。右も左もわからないまま給与計算のフォローや休職者の面談などをやっていました。そのうえ、医療職の募集に対しても、「この金額で採用したい」や「募集はこの金額で掲載してていいのか」など、四六時中質問が入ってきて、人事権についてこれまではどうしてたの?と労務や現場に聞くと「わからない」とのこと。どうやら業務委託の労務コンサルが決めていたようです。労務や給与の仕組みが整っておらず、驚くような方法で運用されていました。
実際に給与支給日が近づくにつれて状況が見えてきましたが、上司のやろうとしていることは給与計算の内製化。ただ、労務コンサルはできないと言っている。理由は直前の条件変更や労務担当にしっかり届くレポートラインができておらず、現場で口約束もあったり・・・
そのうえ、今後は内製化にあたって給与計算シートを変更してそれが複雑すぎて労務担当が対応できないものだったり、勤怠管理のシステムも変更したばかり、給与内訳の変更(スタッフ通知せず)だったりとスタッフの理解と準備が全く進んでいない状態でした。
給与支給日の直前になって賞与の金額を決めるための打ち合わせをしたりと、これではミスが絶対出ると思い、僕は問い合わせ担当を労務コンサルが対応している窓口に一本化しておきました。
案の定、スタッフからの問い合わせやクレーム、不安が給与支給日から何十件も入って、それに労務コンサルが回答。支給漏れを僕と労務担当で振り込むという最低限の対応でした。
心身の限界と休職
その対応をしていた直後、また翌月には次回の昇給の時期やインセンティブの件、労務士変更など、上司からの好きにやっていいですよと言われたので、一本化の提案をするとそれは無しにしましょうという反応。労務担当もストレスに耐えきれず辞めてしまいました。そのうえ上司は業務委託の労務コンサルも契約を切るとのこと。
唯一、僕と話がある程度できていた労務コンサルの契約解除はさすがに無理があるだろうと思って止めましたが、そのコンサルは元々上司と同じ職場の人で、法人への入職を断って業務委託としていたことは、こうなることがある程度わかっていたからとのことでした。方向性もコロコロ変わり、担当者や役割、権限も曖昧、事務局を見る上司が労務に関する知識不足。これでは僕は責任者を到底引き受けられないと伝えました。
すると、部署異動や待遇の変更を打診され、あまりの対応に、あ、この人とは仕事していくのは無理だな…と危険を察知したのか、僕は会社に行く気持ちもなくなってしまいました。動悸や眩暈もするようになってしまい、オンラインで心療内科を受診。2回目の時に「適応障害・うつ症状」の診断を受けて1か月の休職に入りました。
妻の一言と新しい気づき
妻にも相談しましたが、これまでの転職や仕事でも、合わない人がいるといつも突発的に自分で決めたりしてそのことばっかりになっちゃうよね。そもそものところがあると思うから、大人の発達外来でも受診してきたら!?と言われたときにはっと気が付きました。ASDとかADSDとか、特徴を見てみると、あれ?これもしかしたら当てはまるかも…
疲弊していた気持ちの時、妻から言われた一言が最初の気づきにつながりました。早速僕はそんな外来があるのかと調調べてすぐに予約をいれて受診しました。初診時は簡単な問診だけでしたが、来週には発達スクリーニング検査を受ける予定です。
特性に気づいて脳がほぐれた瞬間
他者理解ばかりで自己理解はできているつもりでしたが、これは違うんだ。自分なんだ。とこれまでを振り返ってもそうだし、人との境界線がよくわからなかったり、過度に作業に集中しすぎたり。今回は分析しすぎたりした結果こうなっているのですが、これは強みでもあり、弱みでもある「特性」なんだ。ということに気がついたときにショックもありましたが、それよりもカチコチになっていた脳が「ほぐれる」感じがしました。
キャリアコンサルタントになった自分がキャリア迷子になってしまっているのは自分の「発達特性」ができていなかったからなんだ。あれこれ分析しはじめたら、それは雑念、特性がでてるんだね。と理解してラベリングする。無理に止めようとしない。手放していくのは大変かもしれませんがホントに大きな気づきだなって思いました。
まとめ
休職は決して「弱さの証明」ではありません。
特性と環境のミスマッチから起きただけ。
そう気づけただけで、私は少し楽になりました。
同じように悩んでいる人にも、この気づきを伝えたいです。

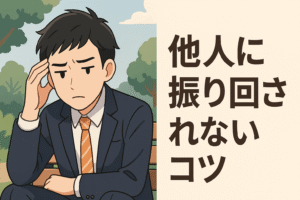



コメント